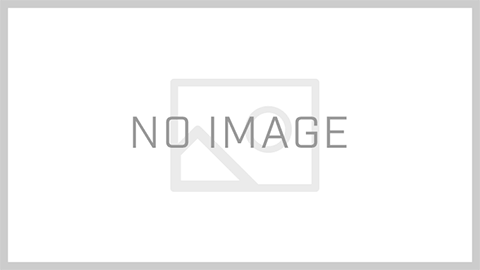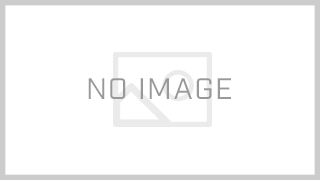恩徳讃は、真宗宗歌よりももっとお馴染みの曲ですが、いくつも種類があるのをご存じですか?
内容(歌詞)は、親鸞聖人の御和讃からいただいているので同じですが、曲が3種類あります。
宗派によってとか、地域によってとか、いろいろあるみたいですが、私たちにとって最も馴染みのある曲は「Ⅱ」ということになっています。ので、時々「恩徳讃Ⅱ」と書いてある場合もありますね。
さて、この曲のワンポイント・アドバイス。
「音程の高低に惑わされない」
どういう事かと言いますと、私たちが歌うこの「恩徳讃」。慣れているのであまり違和感はないかもしれませんが、かなり低い音から、かなり高い音まで、音程の幅が広いという特徴があります。
ですが、1音1音、折れ線グラフで追っていくようにして歌っていると、とてもカクカクした感じに聞こえてきますし、何より、言葉の語感と一致しないため、違和感があるように聞こえてしまいます。
では、どうすれば良いのか??
もちろん、楽譜に書いてある音を勝手に変えるわけにはいきませんし、音はそのまま追っていくわけですが、「フレーズの音程の方向性を見定める」ことで、「単語」や「音」ではなく「句」や「文」の大まかな目的地をイメージしてみましょう。
◎具体的には・・・
1)如来大悲の恩徳は:全体に、音程は上昇していきます。
2)身を粉にしても奉ずべし:全体に、音程は下降していきます。
3)師主知識の恩徳も:上昇
4)骨をくだきても謝すべし:下降
となっていることが、おわかりでしょうか??
つまり、大きな流れをみてみると、
「上がって・下がって、上がって・下がる」
という流れで出来上がっていることが見えてきます。
音程が上昇していくとき。宗教音楽においては、「天に上る」「地上から天へ」というような思いを込められて作られていることが多々あります。
あるいは、音程が下降してくる場合は、例えばキリスト教音楽においては、「天使が舞い降りてくる場面」とか「天から光が降り注ぐ場面」などをイメージした音型に使われることがあります。
恩徳讃は、これは、れっきとした宗教音楽、いわば祈りの音楽です。
キリスト教の音楽のルールが、そのまま当てはまるということではありませんが、
例えば、
音程が上がっていく部分では、阿弥陀様を見上げて手を合わせているようなイメージ。
音程が下がってくる部分では、阿弥陀様の優しいお顔が、私たちを見守ってくださっているようなイメージ。
そんな、まるで仏様と対話をしている(かのような)イメージをもって歌ってみてはいかがでしょう?
決して、一方通行ではない、摂取不捨の誓いが、慣れ親しんだ音楽を紐解いていくと、見えてくることもある(のかも?)
集会のしめくくりの挨拶というだけではなく、少し、「祈りの音楽」という要素について気に留めていただくと、いつもとは違った味わいがあるかもしれませんよ。