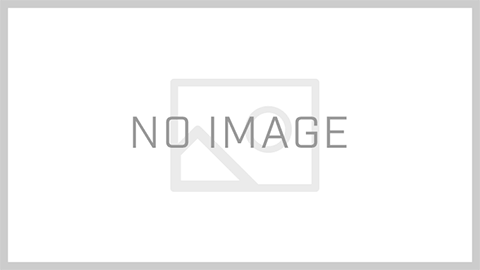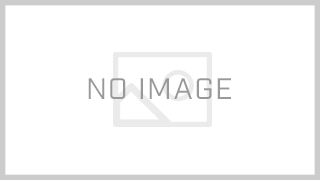「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌イメージソング」として作曲された曲だそうです。新しい曲なんですね。
歌う人、聴く人がそれぞれ、お子さんやお孫さんの事、両親や祖父母など、大切に思ういろいろな人の顔が思い浮かびます。また、今の事、昔の事、これからの事など、歌う時・聞く時々によって、様々な思いが巡るのではないでしょうか。
ぜひ、いろいろな思い出や、大切な人たちの顔を思い浮かべながら歌ってみてください。
<ワンポイント・アドバイス>
さて、今回のワンポイントは、「なんまんだぶつ」。
言わずもがな、
「南無阿弥陀仏」のことですが、
歌詞の一つとして入っていると、普段の「南阿弥陀仏」(なんまんだぶ、なまんだぶ)の気持ちと、うまくつながらないということはありませんか?
かくいう私がそうでした。歌ってみたは良いけれど、明らかに大切な言葉なのに、メロディに流されてしまって、かえって難しいと感じました。
なぜ、そうなるのでしょうか??
それは「自分の言葉ではない」からです。
当たり前ですが、私たちがこうして歌っている歌は、
誰かが綴った詩に、誰かが曲をつけた(逆もありますが)ものを、歌わせていただいています。
共感できる部分はもちろんありますが、
「なぜ、この言葉にしたのか」とか、「なぜ、こんなメロディなのか」とか、そんなことを想像しながら歌わなくてはいけません。
(というか、それが合唱の楽しみの一つでもあるのですが・・・)
この「なんまんだぶつ」という言葉にしても、
リズムも、音程も、回数も、全て楽譜に書いてありますよね?
「よし、おまけにもう1回!」というわけにはいきません。
何げなく「いい曲だなー」と歌っていると、私たちが思っている以上に、「受け身」になってしまいがちです。
では、どうしたら良いでしょう?
リズムも、音程も、回数も。場合によっては、大きささえ指定してある「楽譜」「曲」を、
いかに、わたしたち自身の言葉として紡いでいくか?
それが、「想像力」です。
冒頭にも「いろいろな人の顔が思い浮かぶ」という事を書きましたが、
歌う私たちが、その曲の中にある言葉、メロディの一つ一つや、あるいは休符にさえ、どんな意味があるのかを考えたり、あるいは、どんな願いを込めたいか考えることで、曲が咀嚼(そしゃく)され、初めて「自分のことば」として歌えるようになるのではないかと思います。
少し、抽象的な話になってしまいましたので、具体的なポイントも。
この曲では、初めに「なんまんだぶつ」を「2回繰り返して」います。
なぜでしょうか。1回目と2回目を、どう捉えるかで、歌い方は大きく変わります。
当然、「何となく2回リピートする」ということはありません。
この「2回」を曲(メロディ)から分析してみましょう。
1回目と2回目、音程が高いのは1回目。やや低めで2回目が歌われていますね。
高い音程と、低い音程。
少なくとも、作曲をされた指方先生は、この2回を「音程」という形で色分けされたわけです。
一般的に、高い音程のところは強く、低い音程のところは小さく表現されることが多いので、
1回目は、やや強く
2回目は、控えめに
歌うと、メリハリがつくかもしれません。
が。
そういうことではなく、
なぜ、1回目は高く(強く)
なぜ、2回目は低く(控えめ) なメロディが割り当てられているのかを、想像するというのが、
今回のポイントです。
どんな気持ちの変化があるのでしょう。
あるいは、どんな場面を表現しているのでしょうか。
考え方は、いろいろだと思います。
まずは、皆さんお一人お一人が考えてみてください。
そして、なぜそう思うのかも、ぜひ考えてみてください。
大切なのは、想像してみること。そして、試してみることです。
皆さんの、いろいろな考えを、次集まった時にはぜひ聞かせてくださいね!