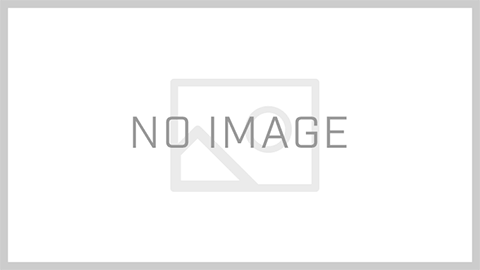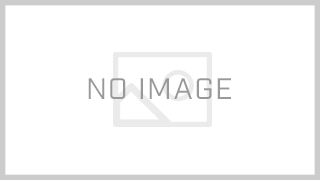2020年は、新型コロナウイルス蔓延の影響で、いろいろなことが自粛されたり、中止されたり、縮小されたりと、経験したことのない大変な1年でした。
極念寺では、報恩講はお勤めしましたが、それでも、いろいろなことを縮小せざるを得ませんでした。
その1つが「お華束」です。
例年、お華束つきや、お華束盛りは、地域の門徒さんたちにお手伝いいただいて作業しています。
今年は当然、みなで集まってわいわい作業するなどということはできず。
住職と坊守が悩みに悩んで考案した、2020年版のお華束が、こちら。。

お供え用の砂糖を、お華束風に積んでお飾りしました。
遠目に見ると、それほど違和感もなく、お参りいただいた方にも、なかなか好評(?)でした。
嘆くばかりでなく、あれこれ工夫してみるって、大切だなと思いました。
さて、話が横道にそれてしまいましたが・・・
金子みすゞさんの、やさしい言葉で綴られた「報恩講」。
昔懐かしい、報恩講の情景が思い出されますね。
<ワンポイント・アドバイス>
今回のワンポイントは、
「楽譜の細かさに、惑わされない」ということです。
この曲に限ったことではありませんが、
日本語の1文字1文字に対して、音符1つずつを割り当てると、どうしても音符が細かくなってしまいます。
この曲も、ざっと見ると、♪(十六分音符)がずらーっと並んでいて、とても忙しく見えてしまいます。
こういう曲を練習するときには、
①まず、メロディを体になじませる
②メロディに歌詞を乗せる
という順番で取り組むことが有効です。
一見、めんどうで回りくどいようにも見えますが、いきなりメロディと歌詞を同時進行しても、どっちつかずになってしまいます。それこそ、忙しくて詩の内容は入ってきませんし、細かい音符にひっぱられて、カクカクしたり、日本語の語感が損なわれた歌になってしまいがちです。
なので、まずは、鼻歌的に、メロディを体になじませてみてください。
リズムは、多少違っても問題ありません。
ハミングや、ルルルなど、歌詞を乗せずに、さらっと歌える程度になったら、ここでようやく詩の登場。
馴染んだメロディに、言葉を乗せていきますが、この時に、やはり音符1つ1つに目を奪われるのは良くありません。
例えば
「お番」の晩は 雪のころ、 雪はなくても 暗のころ
という楽譜1行目。
/おばんの/ /ばんは/ /ゆきのころ/ /ゆきはなくても/ /やみのころ/
と、言葉のまとまりで、楽譜にしるしをつけてみましょう。
単語、文節、、文章、、、
日本語としてのまとまりが意識できると、ずいぶん歌いやすくなるはずです。
そして、それぞれしるしをつけた、初めの1文字めを、少し丁寧に歌うようにしてみてください。
(「強く」ではありません!)
音符は一見細かいですが、語感を意識して歌うことで、ずいぶん日本語らしくなります。
不思議なことに、先にメロディから練習することで、かえって言葉を意識しやすくなるのです。
さらに言えば、初めのうちは、多少リズムやメロディが違っていても問題ありません。
音程、リズムに臆病になると、語感が生きてきませんので、少々のミスやズレは恐れずに、思い切って歌いましょう。「語る」と言ったほうが、良いかもしれません。
歌う私たちが、歌うとともに「語れる」ようになって初めて、聴いている人たちが、その情景を思い浮かべるようになるのです。
ぜひ、おためしあれ。。
ちなみに、
ピアノパートだけだと、ちょっと歌いにくいかもしれませんので、
恥ずかしながら、私たちの歌が入ったバージョンも、そっと置いておきます・・・。
なんと、初、多重録音です!!
(ピアノと、歌それぞれを、全部別々に録音して重ねてみました。これで、リモート合唱もできるかも?!)